賃貸オーナーが、家族信託を検討すべき理由とは?
オーナーが認知症になった場合、賃貸経営はどうなる?

「もし自分が将来、認知症になってしまったら…賃貸経営を続けられるのだろうか?」
そんな不安を感じているオーナー様も、いらっしゃるのではないでしょうか。
厚生労働省によると、2040年には「高齢者の約6.7人に1人が認知症になる」といわれています。
オーナー様が認知症になってしまった場合、以下のようなリスクがあります。
● 契約が無効になる可能性がある
…意思能力が不十分だと各種契約(売買、賃貸管理など)が、無効になるおそれがあります。
● 管理に関する判断ができなくなる
…空室対策や修繕の判断、入居者対応など、日常的な賃貸管理がスムーズにできなくなる可能性があります。
●相続や将来の対策ができなくなる
…認知症になると、生前贈与や相続対策が進められなくなります。
以上が賃貸経営の認知症リスクです。
これまで賃貸経営のリスクといえば、「空室」や「災害」が中心でした。
しかし、これからは「認知症リスク」も見逃せない課題であり、元気なうちに対策を考えておくことがとても大切です。
“認知症リスク”への備えとして注目される「家族信託」
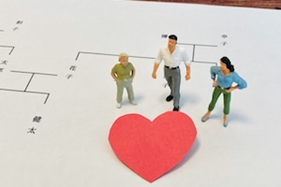
今、認知症リスクへの対策として、不動産業界で注目されている財産管理の方法が「家族信託」です。
家族信託とは、ご自身の大切な財産(アパートなどの賃貸物件を含む)を、信頼できるご家族に託し、将来にわたって管理・運用・承継してもらう仕組みです。
家族信託を活用することで、得られる主なメリットは以下の3つです。
・認知症などで判断力が低下しても、財産が凍結されずに済む
・元気なうちに、「どの財産を、誰に、どのように」引き継ぐかを決めておける
・遺言機能を活用すれば、信託終了後の財産の引き継ぎ先を指定できる
その結果、家族信託を活用すれば、認知症になっても、円滑に財産を管理・運用・承継していけるのです。
「本当に家族信託って広がっているの?」と感じる方もいるかもしれません。
家族信託そのものを示す公式な統計は少ないですが、「民事信託契約」の件数から、その広がりが見えてきます。
たとえば、公証役場で作成された件数を比較すると…
・2018年:2,223件
・2023年:4,434件
5年でほぼ2倍に増加しており、「家族信託は確実に広がっている」と言えるでしょう。
家族信託の基本的な仕組みをやさしく解説

次に、家族信託の基本的な仕組みを確認していきましょう。
たとえば、賃貸オーナーである親(委託者)が、将来に備えて子(受託者)に賃貸物件の管理を任せたいと考えたとします。
この場合、親子で「信託契約」を結び、アパートなどの物件(信託財産)を子に管理・運用してもらう形をとります。
さらに、物件から得られる家賃収入や売却益などを受け取る人(受益者)を親自身に設定しておけば、オーナーはこれまで通り、安定した収入を得続けることができます。
つまり、家族信託を使うと、オーナー様は収入を得る権利を持ちながら、実務をお子様に任せることができるというわけです。
「財産を家族などに任せる仕組み」としては、「成年後見制度」もよく知られています。ただし、成年後見制度は家庭裁判所の監督下で財産管理を行うため、資産の積極的な運用・処分には制限があり、新たな契約や売却などでは都度、許可が必要となります。
「家族に管理を任せながらも、自由度の高い資産活用をしたい」というオーナー様には、家族信託の方が相性がよいケースが多いでしょう。
不動産会社を窓口に家族信託を進めると、以下のようなメリットが得られます。
・信託後の賃貸経営(空室対策・修繕・売却)も一緒に相談できる
・信託スキームと資産戦略(資産の組み換えや出口戦略)をセットで考えられる
ただし、信託契約書の作成や登記は司法書士の専門分野なので、不動産会社と司法書士が連携して進めるのが基本です。
●2.信託する資産を決定する
家族信託は、オーナー様(委託者)が信頼するご家族(受託者)に、財産の管理や運用を任せる仕組みです。そのため、「どの財産を、誰に、どのように」任せるのかを具体的に決める必要があります。この段階では、受託者になる方だけでなく、他のご家族とも話し合っておくことで、後々の相続トラブルを防ぐことにつながります。
●3.専門家に手続きをしてもらう
2で決めた内容を「信託契約書」として書面にまとめます。それを公正証書にしておくとより安心です。
不動産会社に、家族信託に詳しい司法書士を紹介してもらえば、スムーズに進みやすくなります。
もし、お付き合いのある司法書士がいれば、その方にお願いするのも良いでしょう。
なお、信託契約書を作成したあとの手続きは、資産の種類によって異なります。
・不動産の場合:法務局で信託登記(名義の変更)の必要がある
・現金や預金の場合:信託専用の口座を作り、そこへ資金を移す必要がある
家族信託の費用が気になるオーナー様も多いと思います。
専門家に手続きを依頼した場合、一般的に30万円から100万円程度の費用がかかるといわれます。ただし、この金額はあくまでも目安であり、信託財産の種類や総額などにより上下します。
賃貸オーナーが家族信託を利用する際の注意点
ここまで見てきたように、家族信託は財産の管理や承継を柔軟に行える便利な仕組みです。ただし、いくつか注意すべき点もあります。
・受託者以外の相続人から「遺留分侵害額請求」があった場合、対抗するのが難しい
・相続税や贈与税の節税効果は限定的であることが多い
このように、家族信託を利用しただけで、相続や贈与の課題がすべて解決するわけではありません。
また、残債がある物件を信託財産とする場合、融資元の金融機関の承認が必要となります。そのため、家族信託だけに頼るのではなく、ほかの対策と組み合わせて進めることが大切です。
あわせて読みたい
-
相続
遺言書にまつわる注意点やトラブル ④遺言書を絶対に作るべき人・その2
遺言書を絶対に作るべき人その2は特別受益があるときです。 ▼特別受益とは? 民法九〇三条では「特別受益」について「生計の資本として贈与を受けた」と 規定していますが、一般的な贈与に..
-
相続
家族信託を知ろう (1)認知症への備えとなる仕組み
▼7人に1人が認知症に 認知症高齢者は2030年には523万人、高齢者の約7人に1人となる推計が厚生労働省研究班により示されました。今、親の認知症は誰にとっても身近な心配事です。 認..
-
相続
相続対策として生命保険の活用
◆遺産分割の対象外 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。しかし、生命保険金は、契約上指定された受取人が自分の固有の権利として取得します。 夫..
-
相続
AIによる相続税調査の導入(2025年夏~)調査拡大の懸念
国税庁は2025年夏から、相続税の税務調査に人工知能(AI)を本格導入すると発表しました。今回、気になるその内容について取り上げます。 ▼相続税調査にAIを本格導入 2025年夏から、国税庁は..
-
相続
遺言書にまつわる注意点やトラブル ④遺言書を絶対に作るべき人・その1
▼遺言書を絶対に作るべき人 遺言書を絶対に作るべき人“その1”は、子供がいない人です。 配偶者は必ず法定相続人になりますが、子供がいれば子供と配偶者が法定相続人となります。子供が既に死亡してい..
-
相続
遺言書にまつわる注意点やトラブル ③自筆証書遺言補完制度
自筆証書遺言書保管制度 「自筆証書遺言書保管制度」は、普通の人が独力で遺言書を作る前提で制度設計されたもので、法務局が公式サイトで懇切丁寧にやり方を説明してくれています。そのため、最初に作る遺..
-
相続
賃貸物件を活用した相続対策のポイントは?
賃貸物件は相続を意識して取得・所有することが重要です 相続税とは、不動産や金融資産などの相続資産から非課税分(または控除分)を差し引いた金額をもとに計算されます。 資産を現金や預金で持..
-
相続
遺言書の確認をしておきましょう
被相続人が「遺言書」を残しているかどうかの確認をしておくことで、遺産分割相続をスムーズに行うことができます。 遺言書には3種類あります。 遺言書がある場合、遺言者の亡くなった日に最も近い日..
-
相続
遺言書にまつわる注意点やトラブル①
遺言書の有効性と注意点 結論から言うと、財産がある人もない人も、遺言書を作成しておくべきです。 なぜなら、遺言書がないと、残された相続人が遺産分割をしなければならないからです。今回、遺..
-
相続
不動産を含む遺産の分割
相続が発生した場合、遺産は相続人の共有のものとなります。 誰がどのような遺産(相続財産)を受け取るか、また、どんな手続が必要なのかを確認しておくことが必要です。 分割しにくい賃貸住宅等の不動..
-
相続
もしもの時、もめない!慌てない!後悔しない!そのために
オーナー様にもしもの事が起きたとき、何も対策を行っていないと、遺産分割協議でもめてしまい相続人が確定するまでに時間がかかってしまう。 その場合、「賃料の送金口座」、「新たな入居者との賃貸借契約の..
-
相続
一次相続・二次相続対策を知る
【第一回】相続税の基本の計算 相続や遺贈によって遺産を取得すると相続税が発生する可能性があります。相続税の節税にはさまざまな方法があり、適切な方法は個別の状況によって異なります。中には、インタ..